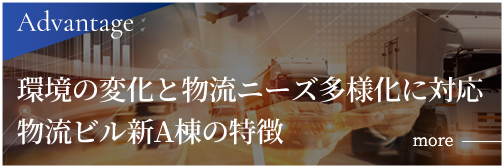サプライチェーンとは?メリットとデメリットについて解説
目次
- すぐにサービス内容を知りたい方はこちら
- 無料相談
- 資料ダウンロード >
本記事では、サプライチェーンの概要や管理方法、マネジメントでえられるメリットとデメリットを解説します。
最後まで本記事をお読みいただくことで、サプライチェーンの概要や詳細な情報が得られるでしょう。
サプライチェーンへの取り組みをお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

サプライチェーンとは
サプライチェーンとは、製品が製造、輸送、販売などを経て顧客の手に渡るまでの一連の流れを指します。
製品は「原材料の調達」→「生産」→「輸送」→「販売」というフローを経て顧客のもとに届きますよね。
消費者に供給するまでには、さまざまな業務がチェーンのように連鎖的につながっていることから、一連の業務をまとめてサプライチェーンと呼ぶようになりました。
サプライチェーンは多くのフローを必要とするため効率化・最適化が求められます。
バリューチェーンとの違い
バリューチェーンはサプライチェーンと似た響きを持ちますが意味は異なります。
バリューチェーンとは、製造から消費者の手にわたるまでの各業務の中で、各部署が生みだした価値を分析することを指します。
バリューチェーンとサプライチェーンでは、着目点が異なります。
サプライチェーンは、顧客に届くまでの一連のモノやお金の流れを注視したものです。
一方バリューチェーンでは、各業務が生みだす価値に目を向けます。
「製造部門では製品の安全性を担保する」「配達業者は顧客のもとへ製品の供給をする」など、各業務の中で、それぞれ異なる価値を生みだしています。
- サプライチェーン…モノやお金の流れに着目
- バリューチェーン…各部署が生みだす価値に着目
サプライチェーンの具体例
サプライチェーンの具体例として、スーパーマーケットの野菜をあげましょう。
製造から販売までの一連の流れには、農家などの生産者、スーパーマーケットなどの小売店といったさまざまな企業、人員が絡んでいます。
サプライチェーンの中には、多くの企業や人材が携わっていることが分かります。
サプライチェーンの抱える課題
サプライチェーンの抱える課題は、ビジネスモデルの多様化によって、複雑化した業務に対処しきれていないことです。
例えば、近年インターネットを用いたEC販売の需要が高まっています。
インターネットを用いたEC販売では、店舗販売よりも多くの倉庫や配達員を確保する必要があります。
ビジネスモデルの多様化によって、サプライチェーンの各業務は複雑化しているのです。
サプライチェーンマネジメントが注目される理由
ビジネスモデルの多様化とともに複雑化したサプライチェーンに対処するために、サプライチェーンマネジメントが注目されるようになりました。
サプライチェーンマネジメントでは、サプライチェーン全体を管理して最適化をはかります。
サプライチェーンマネジメントに取り組むことで、複雑化した各フローの弱点を分析でき、サプライチェーン全体の効率化・最適化がはかれるのです。
サプライチェーンマネジメントとは?
サプライチェーンに関わる各業務の見直しをおこない、供給までの流れを最適化させることをサプライチェーンマネジメントといいます。
サプライチェーンマネジメントでは、製品開発をおこなう企業内の効率化だけでなく、配達業社など他の企業との連携も効率化する必要があります。
サプライチェーンマネジメントの概要
続いて、サプライチェーンマネジメントの概要を解説します。
サプライチェーンマネジメントは、顧客がどの状態の在庫に注文をするかによって分類されます。
下記の7つがサプライチェーンマネジメントの分類です。
- 在庫販売(Ship to Stock)STS
- 見込生産(Make to Stock)MTS
- 受注組立(Assemble to Order)ATO
- 受注仕様組立(Configure to Order)CTO
- 受注加工組立(Build to Order)BTO
- 見受注生産(Make to Order)MTO
- 受注設計生産(Engineer to Order)ETO
順に解説します。
在庫販売
「在庫販売(Ship to Stock)STS」とは、顧客が在庫を実際に見てから注文するパターンを指します。
店が先に商品の仕入れを行い、顧客が店頭などで商品を見てから注文し販売する一般的な実店舗の形式です。
在庫販売の例
- スーパーマーケット
見込生産
「見込み生産(Make to Stock)MTS」とは、企業があらかじめ売れる製品数に予測を立て、販売計画を立て、生産を開始する形態のことです。
先に商品を用意している建売住宅や店舗型のアパレル販売などが、在庫販売に該当します。
見込生産の例
- アパレル
- 建売住宅
受注組立
「受注組立(Assemble to Order)ATO」は、顧客の注文を受けてから最終の組み立てをするパターンを指します。
受注組立の例
- パソコンなど
受注仕様組立
カタログなどから選んだ顧客の注文に従って、組み立てを行い納品するのが「受注仕様組立(Configure to Order)CTO」です。
広義では、この次に紹介する「 受注加工組立(Build to Order)BTO」に含まれることもあります。
受注仕様組立の例
- 取引先企業の製品に対応した、BtoB製品など
受注加工組立
「受注加工組立(Build to Order)BTO」とは、顧客の注文後に標準規格の商品を組み立て、納品するパターンです。
「受注仕様組立(Configure to Order)CTO」ではオーダーごとに仕様を変更し生産するのに対して、「受注加工組立(Build to Order)BTO」では標準のみ製品を生産します。
受注加工組立の例
- パソコン
- 自動車
- 「 受注加工組立(Build to Order)BTO」…注文→標準製品を生産
- 「受注仕様組立(Configure to Order)CTO」…注文→仕様を変更して生産
受注生産
顧客の注文を受けてから原材料を調達、生産し納品するのが「受注生産(Make to Order)MTO」です。
例
- オーダーメイドハンドメイド製品の販売など
受注設計生産
顧客の注文後に、設計、材料調達、製造をおこなうパターンが「受注設計生産(Engineer to Order)ETO」です。
「受注生産(Make to Order)MTO」と異なるのは、注文後に設計からおこなう点にあります。
受注設計生産の例
- 受託ソフトウェア開発など
- 「受注生産(Make to Order)MTO」…設計→注文→原材料の調達→生産
- 「受注設計生産(Engineer to Order)ETO」…注文→設計→原材料の調達→生産
また、倉庫業について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
サプライチェーンマネジメントのメリット
サプライチェーンマネジメントをおこなうことで5つのメリットが得られます。
各情報を一元管理できる
サプライチェーンマネジメントの1つ目のメリットは、情報の一元管理ができることです。
サプライチェーンには、製品の製造から顧客の手に渡るまでのすべての物・業務が含まれるため、管理すべき情報は多岐にわたり複雑化します。
サプライチェーンマネジメントをおこなうことで、サプライチェーンの込み入った情報を管理しやすくなるのです。
適正在庫化が可能になる
サプライチェーンマネジメントによって適正在庫化が可能になります。
過剰在庫、在庫ロスは企業にとって重大な問題です。
在庫を抱えすぎると、管理費用がかさみ、売り切れずに赤字が発生するなどの問題が起きます。
しかし、在庫をセーブしすぎても、顧客の注文にすぐに対応できず機会損失をまねく可能性があります。
サプライチェーンマネジメントによって在庫状況を把握することで、重要な在庫管理が適切におこなえるようになります。
関連記事:在庫管理とは?物流業界における在庫管理の重要性と課題
素早い供給が実現する
サプライチェーンマネジメントに取り組むことで、素早い供給が実現できます。
販売までの早さは、企業の競争力を維持する上で重要です。
サプライチェーンマネジメントでは、各フローの最適化を目指すため、全体の生産スピードが向上します。
供給までの時間を短くすることで、顧客のニーズにいち早く答えることが可能になるのです。
グローバル化に対応できる
サプライチェーンマネジメントによって、企業のグローバル化に対応できます。
近年、企業のグローバル化の動きは加速していますが、サプライチェーンの中に海外企業が絡んだ場合、業務はより複雑化します。
サプライチェーンマネジメントをおこなうことで、各工程の管理が容易になるので、海外企業との取引もスムーズにできるようになります。
サプライチェーンマネジメントへの取り組みは、人材不足の改善にもつながります。
サプライチェーンマネジメントで部署の状況を確認することで、人員過多の部署から、足りない部署に人員を追加できます。
結果として、人材の適正配置が可能になり、少ない労働力でも全体の業務がスムーズに進むようになるのです。
サプライチェーンマネジメントのデメリット
サプライチェーンマネジメントのメリットは多くあるのですが、デメリットもいくつかあります。
導入、運用時にコストがかかる
まず挙げられるデメリットは、導入、運用時にコストがかかることです。
サプライチェーンマネジメントに必要なシステムを導入するには、多くの費用がかかります。
また、導入以降も分析や運用を行う専門家を導入する必要があるため、追加費用が掛かります。
導入時や運用時に一定の費用が必要なことは、サプライチェーンマネジメントのデメリットといえます。
物流コストを減らす方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:物流コストとは?費用内訳を減らす方法について
商品開発の際、視野が狭まることがある
サプライチェーンマネジメントに取り組むことで、商品開発の際に視野が狭まることがあります。
サプライチェーンマネジメントでは、需要にこたえるため、販売データを分析して洗い出した人気商品の制作を強化することがあります。
サプライチェーンマネジメントで得られた人気商品の情報は新商品の開発に役立ちます。
しかし、マネジメントで得られた既存データの情報ばかりに目がいき、思わぬ需要に気付けないことがあるのです。
隠れた需要を見つけるためにも、商品開発の際はサプライチェーンマネジメントで得られたデータを分析すると同時に、視野を狭めない心掛けも求められます。
サプライチェーンの最適化で業務効率化が可能に
いかがだったでしょうか。
本コラムでは、サプライチェーンの概要や、マネジメントによって得られるメリットとデメリットを解説しました。
「サプライチェーンについてよく分からない」といった方にもサプライチェーンマネジメントが業務効率化に有効であることがお分かりいただけたかと思います。
また、サプライチェーンマネジメントのメリットを最大限にえるためにも、物流の中核である施設の立地や設備は重要です。
株式会社東京流通センターでは、大型マルチテナント型物流施設の新A棟を建設中です。
陸・海・空のあらゆる窓口に近い好立地でありながら、住宅街エリアへのアクセスも抜群です。郵便局、コンビニエンスストア、商業施設等が周辺にあり、サービスも整っています。
「東京流通センター新A棟」を詳しくみる。
サプライチェーンマネジメントをお考えの方は、ぜひ東京流通センターのご利用をお待ちしております。