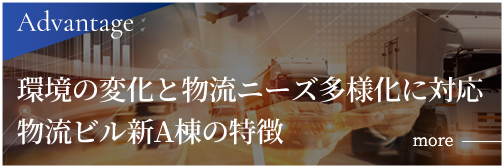倉庫業とは?押さえておくべく倉庫業法を徹底解説
目次
- すぐにサービス内容を知りたい方はこちら
- 無料相談
- 資料ダウンロード >
倉庫業とは?種類ごとに詳しく解説
倉庫は、大きく以下4つの種類に分けられます。
- 営業倉庫
- 自家用倉庫
- 共同組合倉庫
- 上屋・保管庫
なお、国土交通省の所管する「倉庫業法」で定義されている倉庫は営業倉庫のみです。
ここからは、倉庫業の種類について解説していきます。

倉庫業とは
倉庫業とは、荷主から寄託を受けた荷物を倉庫で保管し対価を得る営業形態です。保管する荷物は、原料や加工製品、危険物品などさまざまな種類を取り扱います。
2002年までは、倉庫業を営業するために許可の取得が必要とされていました。しかし物流業界の効率化や競争率の強化に伴う法改正が施行され、許可制から登録制へ変更されたのです。
倉庫の登録申請は、国土交通省に対して「標準倉庫寄託約款」を提出します。そして、倉庫業の登録を受けるためには、以下2つの条件等を満たす必要があります。
・保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であること
倉庫業法
・倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること
登録前に注意すべきことは、利用したい施設を倉庫として使用しても問題ないか、各地方の運輸局や地方自治体へ確認を行うこと。
事前確認が不十分で登録ができないとなると、莫大な経済的損失を被ることになります。
倉庫業は、あらゆる商品や荷物を安全に保管する物流の結節点として非常に重要な業務です。私たちが安心して日常生活を送るためにも、倉庫業務は複雑で厳重な法令が施行されているのです。
また、物流の概要について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:物流とは?物流の概要と種類について、ロジスティクスとの違いについて解説
倉庫業の種類
倉庫業法で定義されている倉庫は「営業倉庫」です。そして、営業倉庫はさらに以下の3つの倉庫に分類されます。
- 普通倉庫業
- 冷蔵倉庫業
- 水面倉庫業
倉庫業の種類は構造や設備、保管内容によって区別されます。
ここからは、それぞれの特性や業務内容について解説していきます。
普通倉庫業
普通倉庫業は、最も一般的な倉庫形態です。対象の物品は以下が該当します。
- 農業
- 鉱業(金属、原油、天然ガスなど)
- 製造業(食品、機械、繊維、化学工業、紙やパルプなど)
- 消費者の財産(家財、美術品、骨董品など)
また普通倉庫業は、次の7種類に分類されます。
- 一類倉庫
- 二類倉庫
- 三類倉庫
- 野積倉庫
- 貯蔵槽倉庫
- 危険品倉庫
- トランクルーム
上記の各倉庫を総称して「普通倉庫」と呼ばれています。
冷蔵倉庫業
冷蔵倉庫業は、10度以下で物品を冷蔵・冷凍保管する倉庫業です。主に取り扱う物品は次の通りです。
- 食肉
- 水産物
- 畜産物
- 農産品
- 冷凍食品
全てを同じ温度で保管するのではなく、物品によって保管時の温度を調整します。
例えば、野菜などに比べて冷凍食品は低い温度で管理をします。鮮度や味を保つために、保管する物品に応じて最適な温度調整が行われているのです。
水面倉庫業
水面倉庫業は、物品を水面で保管するという珍しい管理方法の倉庫業です。別名「水面貯木庫」と呼ばれています。取り扱う物品は原木(第5類物品)です。
陸地ではなく水面に浮べて保管するのは、原木が乾燥して割れてしまうことを避けるため。倉庫までは木を山で切り出した後に河川を利用して運び、海や貯蓄場に浮かべて管理します。
普通倉庫の種類
普通倉庫は7つの種類に分けられます。
それぞれの概要について、ご紹介します。
1~3類倉庫
1類倉庫は、みなさんが想像する一般的な倉庫を指します。「建屋型営業倉庫」とも呼ばれています。
1〜3という数字は設備や構造基準によって分けられており、1類倉庫は最も高い水準です。防水・耐火・防湿・遮断性能に優れていて、危険品倉庫や冷蔵倉庫での保管が義務付けられている物品以外は保管することが可能。
日用品や繊維、電気機械など、幅広い分野の物品が対象となります。
2類倉庫は、1類倉庫から防火・耐火性能を除いた、燃えにくい物品が対象です。
塩や肥料、でんぷんなどが対象となります。
3類倉庫は、2類の防火・耐火性能に加えて防湿・防水性能が不要となり、1〜3類倉庫の中で最も制限が緩和されている倉庫です。湿気に強く気温の変化にも影響を受けにくい物品が保管できます。
鉄材やガラス材、陶磁器などが対象です。
野積倉庫
野積倉庫は、倉庫といっても建物ではなく柵や塀で囲まれた特定の区画を指します。この区画は、国土交通大臣が定める防護施設であることや、防火・照明設備が設置されていることなどが条件です。
倉庫で保管する荷物は、法律上の第4類物品が対象となります。第4類物品とは、雨風にさらされても問題のない鉱物や木材、石炭などを指します。
物品を野積(=物品を屋外に積むこと)状態にするため、「野積倉庫」と呼ばれています。
貯蔵槽倉庫
貯蔵槽倉庫とは、農産物や飼料などを積んでいるサイロやタンクと呼ばれる倉庫です。
法律上の第6類物品を保管します。第6類物品とは、容器に入れていない小麦、大麦などの粉状の荷物や糖蜜などの液状荷物のことです。
袋などの容器に入っていない穀物などの保管に最適な倉庫です。
危険品倉庫
危険品倉庫とは、文字通り危険品を保管するための倉庫です。
法律上においての第7類物品を保管します。第7類物品とは、消防法が指定する危険物やガソリン・高圧ガス・液化石油ガスなどが対象となります。また取り扱いには、関係法令の規定を満たすことが求められます。
危険物倉庫は、保管や取り扱いに厳重な注意を払う必要があります。倉庫業法の他にも各自治体で保管の条件が細かく定められている場合があるので事前に確認するようにしましょう。
トランクルーム
トランクルームとは、自宅の財産を収納する延長として保管する倉庫です。
家財や美術骨董品、楽器や書籍など個人の持つさまざまな財産を保管することができます。
対象物品によって、温度・湿度管理などの管理環境が異なることが大きな特徴。レンタル収納やレンタル倉庫とも呼ばれています。
国土交通省の大臣から、一定の性能が備わっていると認定されたトランクルームは「認定トランクルーム」と呼ばれます。
倉庫業のサービス内容
倉庫にさまざまな種類があるように、倉庫業にも商品の特性に合わせた管理体制が求められます。
倉庫業の主な業務内容について、フローごとに解説していきます。
- 検品
倉庫へ届いた商品の数量や種類に間違いないか確認します。 - 入庫
検品が終えた商品から、適切な保管場所まで運びます。在庫数や商品番号の確認も行います。 - 保管
入庫した商品は、適切な保存条件で保管します。 - 流通加工
商品を出荷するための準備を行います。包装やラッピングなどの梱包作業や、ラベル貼りなどの加工業務、機械や家具などの組立業務。 - ピッキング
ピッキングとは、必要な商品を保管先からピックする(=集める)作業のこと。注文書に従って対象の商品を保管場所から取りに行きます。 - 仕分け・荷揃え
ピッキングした商品を配送先に沿って仕分けして、トラックごとに荷揃えします。 - 出庫
集められた商品をトラックに積み、指定の納品時間に合わせて出庫します。
倉庫業法とは
倉庫業法とは、倉庫を利用する人たちの利益を保護するために倉庫業が適正に運営されることを目的とした法律です。
冒頭で触れたように倉庫は大きく4つに分けられ、倉庫業法は「営業倉庫」について定義しています。
営業倉庫を運営するためには、倉庫業法が定めた条件を満たし、規定に沿った書類を指定先へ提出する必要があります。国土交通省の登録がされずに無許可で営業した場合は、罰金や懲役などの刑罰に科せられることがあります。
営業倉庫として運営するための条件は、以下のとおりです。
- 申請者は欠格事由を確認する
- 施設設備基準を満たす
- 倉庫管理主任者を選任する
倉庫業法の目的
倉庫業法の目的について、国土交通省のHPでは次のように定義されています。
この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)
つまり倉庫業法とは、倉庫の利用者である「荷主」が預けている貨物に不利益が被らないよう保護する法律。荷主の利益を守り、管理期間中のあらゆるトラブルを防ぐことが最大の目的なのです。
営業倉庫は、倉庫業法によるさまざまな基準をクリアした倉庫として国土交通省から認定されているため、安全性の高い倉庫として保証されています。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、倉庫業の種類や注意すべき倉庫業法のポイントについて紹介しました。
倉庫業は、単に物品を倉庫へ保管するだけでなく、生産から消費に至るまでの全工程を繋ぐ重要な産業です。倉庫業法の正しい理解が営業倉庫の安全な運営に必要不可欠。
そして、倉庫業法は荷主の利益を守るための法律でもあります。荷主自身が正しい知識を身に着け規制内容を把握しておくことが、自社を守ることに繋がることを覚えておきましょう。
弊社が管理する首都圏の平和島に構える「東京流通センター物流ビル新A棟」は、倉庫業法に基づく条件を全て満たした好立地の物流施設です。
専有面積は約156,000㎡(約47,000坪)、地上6階建の屋上には駐車場も完備しています。
東京モノレール「流通センター」駅から徒歩1分圏内とアクセスが良く、周辺には郵便局やコンビニ、商業施設など多くのサービス施設が整っているので、オフィスとしてのご利用にも適しています。
さらに、24時間365日の有人防災センター管理体制が整っているので、安全性も保証されています。万が一トラブルが発生した際にも即時対応いたします。
首都圏で物流倉庫やオフィス事務所をお探しの方は、まずはお気軽にご相談ください。
「東京流通センター新A棟」を詳しくみる。