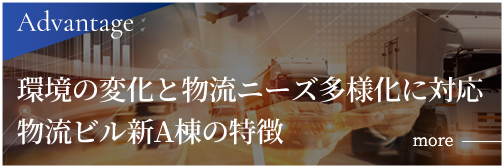物流とは?物流の概要と種類について、ロジスティクスとの違いについて解説
目次
- すぐにサービス内容を知りたい方はこちら
- 無料相談
- 資料ダウンロード >
物流とは
まずは、「そもそも物流とはなにか」を深堀りして解説していきます。

概要
物流とは、商品が消費者に届くまでのモノの流れのことです。
物流と聞くと、商品を保管している「倉庫」や街中を走る運送トラックなどの「配送」をイメージする方が多いかもしれません。
他にも包装や荷役、流通加工、情報処理など、さまざまな機能があります。
それぞれの機能については後ほど詳しく解説しますが、これらの機能が連携することでスムーズに消費者に商品が届けられるのです。
企業にとっては、商品を必要としている消費者に「必要な数」を「必要な場所」に正確に届けることは信頼性にかかわってきます。
物流の市場規模
2022年度の物流の市場規模は約28兆円です。
物流業界にはさまざまな分野がありますが、営業収入でみると、トラック運送業が約19兆円と全体の約7割を占めています。
国内の貨物輸送量は輸送重量(トンベース)ではほぼ横ばいで推移していましたが、2020年度は大幅に減少しました。
国内貨物のモード別輸送(トンキロベース)では自動車が約5割、内航海運が約4割を占め、鉄道が占める割合は全体の5%程度でした。
業界別でトラック活用状況をみると、日用品、金属鉱、食品工業品が上位を占め、いずれもトラック活用率は80%を超えています。
つまり、短距離輸送はトラックが多く、中・長距離輸送になると海運などの大型輸送機関が使われています。
物流施設とは
後述する物流6大機能のうち4つ(保管・荷役・加工・包装)を担っています。
残る2つの「輸送・配送」「情報システム」も無関係ではなく、荷役の機能がないと輸配送できません。
また、物流施設にはモノだけでなく情報も集積しているので、6大機能すべてをカバーしているといえるでしょう。
6大機能のそれぞれに発生する作業や活動にかかる費用の総称である物流コストの45%が物流施設で発生しています。
物流コストに占める各費目の割合は「輸送費」54.3%、「保管費」17.0%、その他(「包装費」「荷役費」「物流管理費」)28.7%となっています。
物流施設で発生しているコストは、全体から輸送費を除いた部分なので、2021年度の調査では全体の約45%を占めています。
立地は郊外や臨海部に多く、広いスペースが必要で土地代が比較的安いことが理由にあります。
しかし、最近は土地価格の高騰や既存施設の老朽化による建て替えなどの理由で、臨海から内陸部に移転するケースもみられます。
立地条件として重要なのがモノ・ヒトの両面で交通アクセスが良いなど、公共交通インフラの利便性が高いことが挙げられます。
交通インフラが充実している施設は輸送・配送や雇用の面で優位性があるのです。
高速道路のインターが近いか、国道などの主要道路へのアクセスがスムーズかなどはスピーディーな輸送・配送にかかわりますよね。
また、雇用においては駅から徒歩圏内で通えるかが重要です。
駅から離れた場所だと送迎バスを運行したり、従業員用に駐車場を設けたりとコストアップしてしまうでしょう。
物流コストについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
物流と流通との違い
流通とは、生産された商品が消費者まで届けられる一連の流れのことで、大きく分類すると「商流」と「物流」に分けられます。
商流は、商品の所有権移転や金銭取引など取引情報の流れのことで流通活動のモノの流れ以外で発生します。
物流とは、純粋に商品を必要なときに必要な場所へ必要な量だけ運ぶことを指します。
流通は「商流」と「物流」の2つからなる考え方なのです。
関連記事:商流とは?物流との違いと正しく理解しておくことが重要とされる理由
物流とロジスティクスとの違い
物流とロジスティクスは混同されがちですが、ロジスティクスは軍事用語で「兵站」と呼ばれ、昔からあった言葉です。
軍事でのロジスティクスとは、戦地で戦う兵士に武器や食料などを調達する任務を意味し、戦争において滞りなく物資を供給することは重要な仕事でした。
刻々と変化する戦況を読み、スピーディーに過不足なく物資を供給できるかが戦争の勝敗を分けるのです。
物流はロジスティクスのマネジメントを構成するひとつの業務でしかありません。
物流の複雑な流れを一元管理して、より効率化する考え方をロジスティクスといい、物流よりももっと幅広い概念です。
また、ロジスティクスについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
物流の目的は
物流の目的は「空間」と「時間」のギャップを埋め、付加価値を生み出すことにあります。
生産者と消費者の間には「空間」と「時間」というギャップがあります。
空間とは生産地から消費者までの距離、時間とは生産されてから消費されるまでの時間を指します。
生産されたモノがすぐに消費されるとは限らないため、必要なときがくるまで保管し管理することも求められますよね。
かつては商品を届けるまでの時間を短縮させることで、空間のギャップを解消していました。
しかし、オンラインショップでの買い物が増え、多種多様な小口出荷が多い現代では、ただスピーディーなだけでなく、必要なときに必要な量を届けられることが重要になっています。
そのために、後述する物流の機能をフル活用し、効率よく商品を届けられる仕組みを構築する必要があるでしょう。
物流の6大機能
物流というと「輸送・配送」を真っ先に思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
他の「保管」「包装」「荷役」「流通加工」「情報処理」の6つの機能が合わさることで効率的な物流が成立します。
輸送・配送
輸送とは、輸送する物資をトラックや船舶、鉄道、航空機、その他の輸送方法によって、ある地点からほかの地点へ移動させることです。
配送とは「二次輸送」とも呼ばれ、近い距離の小口輸送を行います。
物流センターなどの拠点となる場所から卸売業者や小売店、消費者などにモノを運ぶ場合は「配送」になります。
保管
保管とは、物資を一定の場所に置き、品質や数量の保存など適正な管理のもと、一定期間置いておくことです。
販売の需要に対して、品ぞろえが十分であり、すぐに取り出せる状態であることが大切です。
そのために的確な在庫管理と適切な保管方法でないといけません。
包装
包装とは、物品の価値や状態を維持するため、適切な素材や容器などに収納する作業です。
包装の目的は「取り扱い・保管・販売の利便性確保」や「宣伝・情報の伝達」などがあります。
しかし、最も重要なのが「包装品の保護」で外力から守ったり、温湿度などの環境条件から守ったりと、包装品を守る役割を果たします。
荷役
荷役とは、物流過程のさまざまな場面での物資移動のための作業のことです。
輸送機器への「積卸し」や倉庫内での「運搬」、保管されている物品から必要なモノを取り出す「ピッキング」などがあります。
物流コストは荷役の効率に大きく左右されるので、適切な機器や方法で作業を行うとよいでしょう。
流通加工
流通加工とは、従来生産現場や店舗で行われていた作業を物流センターで行うことで、供給にかかる時間を短くし、多様なニーズに応えようとするものです。
例えば、チーズやチョコレートのワイン向けギフトボックスの販売用セット箱詰めや紳士服や制服のネーム刺繍などが挙げられます。
物流センターで加工を行うことで、発注から納品までにかかる時間を短縮できるうえにコストも削減できます。
流通加工を実現させるためには、ミスを防ぐ仕組みの導入や情報システムの開発・管理などをしっかり行う必要があるでしょう。
情報システム
物流を正しく効率的に機能させるために、情報システムなくしては成立しないといっても過言ではありません。
物流情報システムは大きく「戦略・企画」「計画・管理」「実務」の3つに分けられます。
実務のなかでも倉庫内における保管・包装・荷役・流通加工を支援する倉庫管理システム(Warehouse Management System,WMS)は情報システムの基盤になっています。
ハンディのような読み取り機器を用いて、棚卸し業務や在庫の管理、帳票やラベルの発行まで簡単にできるので、工数削減や人件費削減につながります。
WMSは連携すれば他の倉庫や取引先とも情報を共有できるので、相互管理の意識が働き、適切に運営できるでしょう。
人を介する作業が減る分、人員を削減できるうえ作業自体も標準化できるので、繁忙期などはパートやアルバイトなども大きな戦力になるでしょう。
物流の5つの領域
物流には企業の活動や実態に応じて「調達物流」「生産物流」「販売物流」「回収物流」「消費者物流」と5つの領域があります。
調達物流
原材料や資材を生産者から調達する際のモノの流れを「調達物流」と呼びます。
多品種少量生産が主流となっている現代は「必要なモノ」を「必要なとき」に「必要な量」だけ生産すること(ジャストインタイム化)は在庫コストを減らすことに直結しています。
以前は注目度が低かったですが、今は多くの企業で実践されている考え方です。
生産物流
生産物流とは、倉庫内で発生する物流のことで、調達した資材の保管・管理から包装、発送までの流れを指します。
販売物流
商品を倉庫や小売店を介して消費者に運ぶ際のモノの流れを「販売物流」と呼び、一般的に物流というと、この「販売物流」を指します。
オンラインショップでの買い物が増えている昨今、消費者への直送が大きな割合を占めるようになってきました。
どちらにしても「必要なモノ」を「必要なとき」に「必要な量」を消費者に届けるためには、輸送・配送の効率化や適切な在庫管理が必須でしょう。
回収物流
回収物流とは、ペットボトルやプラスチック、家電などが役目を終えて回収・再資源化される流れのことです。
実践している企業として、アパレルのパタゴニアが挙げられます。
プラスチックをリサイクルして商品を作ったり、壊れた商品を修理して長く着れるようにしたりと、環境に優しい活動で他メーカーと差別化し唯一性を確立しています。
消費者物流
消費者物流とは、一般消費者を対象にした物流のことです。
代表的な例として引越しや宅配、トランクルームや個人向けのレンタルスペースなどがあります。
また、物流企業は卸売業者や小売店をクライアントにしていることが多いため、消費者をクライアントにしている企業のことを消費者物流と呼ぶこともあります。
今後の物流
国土交通省によると、2021年度の宅配便取扱個数は約49億5千万で年々増えています。
そのうちトラックでの取扱は約48億8千万と群を抜いています。
トラック運転手の需要は増えていますが、労働環境や少子高齢化の影響で人手不足になっていたり、若手が少なく運転手が高齢化したりなどが物流業界の現状です。
この人手不足とトラック偏重による環境負荷を解消するために取り組んでいるのが「モーダルシフト」で、輸送機関をトラックから鉄道や船舶へ転換する動きが加速しています。
これによりトータルで輸送距離の短縮になるため、CO2排出量の削減はもちろん、トラック運転手の負担軽減につながりますよね。
従来のトラック輸送は、多種多様な小口出荷が多い現代において必要不可欠な輸送機関です。
今後は鉄道や船舶、航空などの機関とバランスよく活用することが求められていくでしょう。
奥深い物流の世界
物流とは何か?基本から目的や機能、今後の展望まで解説しました。
本記事をきっかけに物流を知ることで、ビジネスの理解が少しでも深まれば幸いです。
輸送機関の多様化や情報システムの活用、コスト削減などにおいて物流センターがもつ意味はますます大きくなるでしょう。
平和島に構える物流施設東京流通センター新A棟は立地、インフラ整備、管理体制のどれも充実した施設です。
流通センター駅から徒歩1分で通勤は快適ですし、高速道路や空港、貨物船など陸海空の交通の便もアクセスしやすく物流拠点として優れています。
物流拠点にお悩みの方は検討してみてはいかがでしょうか。
「東京流通センター新A棟」を詳しくみる。