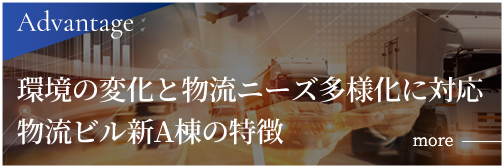3PLとは?概要について詳しく解説
目次
- すぐにサービス内容を知りたい方はこちら
- 無料相談
- 資料ダウンロード >
3PLとは
3PLとは、荷主に代わって第三者(サードパーティー)が最も効率化された物流システムの構築から提案までを行い、物流業務の全てを一気通貫で担う形態のことを表します。
物流とは従来荷主と運送業者の2者間で運用されてきましたが、そこに第三者が介入することでより物流を最適化しよう、という動きです。
物流のアウトソーシングや受託形態に影響を与えたのが3PLです。物流分野において、3PLの存在によって物流業務が効率化されることにより、地球温暖化問題の解決にも寄与すると言われており、国土交通省も支援しています。
また、欧米から広がったシステムは現在でも3PLの市場規模を拡大傾向へと続いているのが特徴です。

国土交通省も総合支援する取り組み
3PLにより物流効率化が実現された場合、得られる効果は2つあると考えています。1つめは「地球温暖化問題への対応」によるCO2排出量の削減、2つめは地域雇用の創出です。そのため、次の3つについて支援しています。
- 3PL人材育成推進事業の実施
- ガイドライン等の策定
- 物流効率化法や物流拠点施設に対する税制特例等による支援
3PLの歴史
アメリカでロジスティックを外注するという概念が1980年代の中ごろから後半にかけて生まれ始めました。
背景には、同時期に実施された規制緩和と情報通信技術の発展があります。
ロジスティックの発展により、人々の物流に対するニーズも多様化し始め、現在の3PLの形態が出来上がりました。
また、ロジスティクスについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:ロジスティクスとは?物流の違いと仕組みについて解説
サードパーティーの定義
サードパーティとは「第三者」のことです。
第三者がいるということは、当然第一者と二者が存在します。
この二者を「ファーストパーティー」と「セカンドパーティー」といいます。
3PL業者は大きく分けて「アセット型」と「ノンアセット型」に分類されます。それぞれ順番に解説します。
アセット型とノンアセット型に分類
アセット型とノンアセット型は物流用語であり、この2つの考え方とサードパーティーの定義を合わせると、消費者の手に渡るまでの一連の流れが網羅できます。簡単に物が消費者の手に届くまでの流れをご説明します。
- サプライヤー・・・部材・原材料の開発や製造を行う
- メーカー・・・調達から製造を担います
- 卸・・・配送
- 小売(問屋)・・・販売し消費者の手元へ
この2から4までの流れは、3PL業者が一気通貫で対応します。
そこで1から4までの流れをもとに、アセット型とノンアセット型違いを詳しく見ていきます。
アセット型
物流サービスを提供する側の物流用語です。三者間で担う役割は次の通りになります。
- ファーストパーティ・・・メーカー
- セカンドパーティ・・・小売(問屋)
- サードパーティ・・・物流業者
アセット型にあてはまる業者は自身で資産を所有しているのが特徴です。資産とは物流倉庫や運送用のトラックがあてはまります。
物流部門が行う業務の委託を一括で受けるため、メーカーとの強固な協力体制をとれます。
ノンアセット型
アセット型が資産を所有しているのに対し、ノンアセット型は資産を所有していません。その代わりに、物流に関するノウハウをメインに提供します。この場合、三者間で担う役割は次の通りです。
- ファーストパーティー・・・荷主
- セカンドパーティー・・・小売(問屋)
- サードパーティー・・・3PL業者
3PL導入のメリット
導入により得られるメリットは5つあります。
これはアセット型・ノンアセット型に関係なく荷主が享受できるメリットです。
それぞれについて順番に解説します。
物流コストの最適化
毎月の固定費が削減できます。物流分野における固定費は次の3つが代表的です。
- 人件費
- 運送費
- 倉庫費
3PLのシステムを構築できれば、上記のようなリソースを3PL業者が代わりに持ってくれるため、「利用した分だけ支払う」という変動費に変えられます。
自社で全ての資産を保つ場合、例えば「今は仕事の量が少ないから」といって、従業員を減らすことも運送に使用するトラックを手放すこともできません。もちろん倉庫も手放すことも容易ではありません。
物流にかかる人的・物的リソースを3PL業者が代わりに持ってくれるので、毎月の固定費を削減できるというわけです。
また、物流コストを抑える方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:物流コストとは?費用内訳を減らす方法について
生産性の向上
生産性を向上させるには、以下のいずれかの条件を必ず満たす必要があります。
- 売上を上げてコストも削減
- 売上を上げてコストは変えない
- 売上はそのままでコストを削減
その中でもベストな状態は「売上を上げてコストも削減」です。
通常であれば、売上が上がるとそれに伴い売上原価も上昇します。
しかしコストを削減できれば利益率が上がり、最終利益も増加。
同様に、売上が変わらなかったとしても、コストを削減できれば利益率が改善でき、最終利益は増加します。
いずれかの条件を満たすためには、売上に対するコストの割合を増やさないことが必須となります。
3PLを導入すれば、売上に関わらず必ず決まった金額で発生する固定費を変動費に変えられるため、一定の利益率を担保できます。
品質の向上
3PLの導入により、経験をもとに得られた知識を提供する側と、実際に動く側とに役割分担ができます。
そのため、それぞれの得意とするところが活用できるので、物流業務の品質向上が期待できます。
発送する商品を傷つけてしまった、到着が遅延してしまうといったトラブルも減少し不良在庫の削減にもつながります。
物流業務の品質が向上することで顧客満足度も上がり、売上の増加にも寄与するでしょう。
労務リスクの排除
物流業界に限らず、人員確保から教育、そして組織としてうまく稼働させるには、お金と時間がかかります。人材には当然退職のリスクもつきまといます。
3PLの導入は外部にプロフェッショナル人材を確保することと同義なので、上記のような人材の確保・教育にかかるあらゆるコストを削減できます。
販路の拡大
3PLのシステムを活用すれば、営業活動をする時間を確保できます。
物流にまつわる業務を外注できるので、営業活動だけでなく新規事業の立ち上げといった新たな取組に割ける時間も生まれます。
3PL導入のデメリット
物流を外注することによるデメリットも存在します。3PLは各アクターが自身の得意な分野を活かす物流システムです。
そのため得意な部分のノウハウは蓄積されますが、不得意な部分のノウハウは蓄積されません。また、物流業界と業務全体を理解できる人材が自社からいなくなる可能性もあります。
それぞれ順番に解説します。
物流人材の空洞化
3PLは物流業務を外注するシステムです。
そのため社内に物流業務の知識やノウハウを持った人材がいなくなります。
3PLによって物流業務を外注することで固定費が削減され、利益率は上がりますが社内に物流のノウハウが蓄積されないことはデメリットと言えるでしょう。
パートナー企業の固定化による弊害
3PL業者にも得意分野と不得意分野があります。
物流業務を委託する会社を一社に限定している場合、上述したメリットを享受できるかは完全にその会社のパフォーマンス次第です。
あらゆる物流業務に迅速且つ正確に対応できるよう、パートナー企業は固定せず、複数の選択肢を持っておくようにしましょう。
自発的な改善提案がでない
物流に精通した人材が社内にいなくなることで、物流業務にかかる自発的な提案が社内から出てきにくくなります。
パートナーである3PL業者におんぶにだっこ状態になってしまう可能性があります。
契約関連の煩雑さ
物流業界で交わされる契約は以下の項目がネックとなって煩雑になる傾向にあります。
- 課金項目名
- 単位
- 料金
この3つの項目は、荷主側から見れば明確にしてほしい部分です。ただ、業界的にみて「標準」といわれるものが明確に定められていないため、不明瞭になる傾向があります。
後々のトラブルを防ぐためにも「何をどれくらいいくらで任せるのか」を明確にし、書面で契約を交わすようにしましょう。
自社のノウハウが蓄積しない
問題が発生したときの対応に欠かせないのが、これまで蓄積してきたノウハウです。
「ノウハウ=経験」なので3PLを導入すれば、自社で直接携わっていない領域のノウハウはどんどん陳腐化していきます。
よって、普段外注している領域で何か問題が発生したときに「何が問題なのか」に気づくことができなくなるのです。
3PL導入の際の注意点
契約締結時に明確にしておいた方がいいことやサービスとコストのバランスなど、事前に知っておいた方がいい部分があります。業務委託なので、契約内容をしっかり決めておかなければ、のちに問題になることもあるでしょう。また、はじめて3PLをする業者とはすぐに成果が出ると考えていてはいけません。1つの業者に固定することは業務の領域を含めて判断する必要がありますが、長期的な計画と判断が必要です。
3PLの導入について、契約締結時に明確にしておくことや、享受できるサービスの質とコストのバランスなど、事前に考慮すべき点は多々あります。
また、3PLはすぐに成果が出るものと考えてはいけません。長期的な視点と計画を持って導入を判断しましょう。
業務委託の5つの範囲について
3PLに限らず、物流の業務委託の内容には5つのポイントがあります。「何をするのか」「何をしたのか」が分かるように、どこまで委託するのか明確に決めておくのがよいでしょう。
- 出荷業務について
- 梱包作業について
- ピッキング作業について
- 仕分け業務について
- 入庫から倉庫での保管について
物流コストの削減に関して過度な期待
「今日導入して明日成果がでる」というものではありません。もちろん誰もがコスト削減とそれに伴う生産性向上に期待をして3PLを導入しています。
しかし、結果が出るには時間がかかります。繁忙期と閑散期の両方を経験したうえで「今の業者のまま続けるのか新たな業者を選定するのか」という判断が必要です。成果を出すには「長期的なプラン」を持つことが大切です。
3PL事業者との連携
社内のコミュニケーションが重要であるのと同じように、委託する業者とのコミュニケーションも重要です。常に情報交換することでトラブル発生の防止や、発生してしまった場合の対処方法をすぐに見つけられます。
繁忙期や閑散期などへの対応
3PL業者に、自社の繁忙期と閑散期を知ってもらうことが必要です。繁忙期と閑散期は会社によって異なります。そのため、繁忙期に適切な行動を3PL業者にとってもらうためにも事前に確認しておくのも良い方法です。委託した3PL業者が、はじめから繁忙期に適切に動けないとわかっていれば、違う業者の選定ができます。まずは自社の計画を把握し、そのうえで委託業者に動いてもらえるかどうかで、業者を選定しましょう。
コストとサービスのバランス
3PLを行う業者は多くあります。そのため、それぞれが自社の特性を出すためにサービスの内容が大きく異なるケースも珍しくありませんが、各社の特徴は大きくわけると次の2つに分類されます。
- 費用は高いが自社に合わせて融通が利く
- 費用は安いがある程度決まったサービスでしか動かない
費用を気にしすぎて安い業者に委託すると、場合によっては自社の依頼内容には合わないかもしれません。仮に、それで閑散期は対応できても繁忙期になれば対応できなくなります。それでは3PLを導入し委託した意味がありません。
一方、費用が高くても自社にあわせて融通が利くサービスであれば繁忙期は助かりますが、閑散期はコストがかかりすぎてしまいます。
このように、どちらを選択すれば費用対効果としてバランスが取れるのかを考えておくことが必要です。
これから物流業務を変える3PL
3PLの導入は、これからの物流システムの主力となる方法です。委託契約の内容や費用面で、どの程度任せられるかがポイントになります。
メリットやデメリットはありますが、国土交通省も総合支援する取り組みだと考えると、取り入れる方がビジネスにおいてメリットが大きいと言えるのではないでしょうか
「東京流通センター新A棟」を詳しくみる。